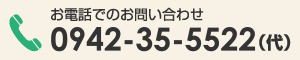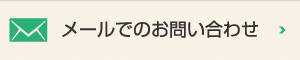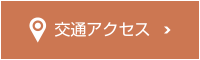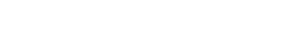イベント開催報告
-
2017.10.01 「がんを考える」市民公開講座を開催しました
聖マリア病院は10月1日、久留米シティプラザで「がんを考える」市民公開講座を開催しました。
当院は、国から指定を受けた「地域がん診療連携拠点病院」です。がんの診療体制を一層充実させるため、本年4月、「緩和ケアセンター」「がん相談・診療支援センター」を新設しました。今回の講座は、がん患者とその家族、がん診療に関心のある地域の医療関係者、一般市民に両センターの機能を紹介し、がん治療や緩和ケア医療の実際を伝えるために開きました。
第1部では、女優でがんサバイバーの仁科亜季子さんが「がんになっても元気に明日へ~今だから伝えられること~」と題し講演しました。自身の4度のがん手術の経験から、病気に負けずに明るく過ごすための「元気」「陽気」「強気」、手術や治療を前向きな気持ちでうけるための「やる気」「根気」、早期発見のために健診を受ける「勇気」の6つの「気」を大切に、PPK(Pin Pin Korori、ぴんぴんころり)で人生を終えることができるように過ごしてほしいと語りました。
第2部のパネルディスカッション「がんになっても元気に生きよう」では、今村豊緩和ケアセンター長がコーディネーターを務め、がん治療や緩和ケアに携わる聖マリア病院の看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーが、聖マリア病院で行われているがん治療や緩和ケア医療の実際、セカンドオピニオン制度、がん相談支援室・臨床心理室での無料相談などのさまざまなサポート体制について、Q&A方式で分かりやすく説明しました。それを受けて、緒方俊郎がん相談・診療支援センター長も交え、4月に新設された両センターの機能を紹介しました。
講座には約280人が訪れ、参加者からは「なにごとにも前向きな仁科さんに勇気をもらった」「病院のサポート体制がこれほど充実しているとは知らなかった」「早期発見、早期治療のために健診を受ける決心がついた」などの声がきかれました。
笑顔で講演する仁科亜季子さん
新設の2つのセンターのスタッフたち
―
講演に先立ち、9月30日、仁科亜季子さんは聖マリア病院でがん治療を続ける約20人の患者のもとを訪れ「痛みや不安で病気に負けないよう、日々楽しいことを考えて、治療を頑張ってください」と励ましました。 -
2017.07.24 九州夢大学の企業研究ゾーンに出展しました
7月24日、『九州夢大学 in 福岡』が福岡国際センターで開催されました。このイベントは、株式会社マイナビが「1日で進学と、その先を考える事のできるイベント」として毎年開催しているものです。会場には九州各地の大学と企業・職業人が集結し、大学説明会ゾーン、企業研究ゾーン、お仕事研究ゾーンに分かれて、各校の学部やゼミの紹介、各企業・職種の特徴や仕事内容を紹介しました。
聖マリア病院は「企業研究ゾーン」に出展し、事務員、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士がそれぞれの職種や病院、医療の仕組みについて紹介しました。ブースには100人を超える学生が訪れ、熱心に耳を傾けていました。

自身の経験を語る聖マリア病院の男性看護師。学生たちは熱心に耳を傾けています -
2017.07.13 脳死下臓器提供の検証会などを開催
1997年に臓器移植法が施行されて20年。聖マリア病院では、臓器提供を希望する患者さんやご家族の尊い意思を、病院全体で支援できるよう、院内体制を整備しています。
その一環として、7月13日に、当院で3例目となる脳死下臓器提供(2017年1月に実施)の事例検証会を開催しました。 検証会には職員約70人が出席。主治医や臓器提供の中心となる院内コーディネーター、関係部門の代表者らが、患者さん搬入から臓器提供に至るまでのそれぞれの活動や反省点、疑問点などを報告しました。また福岡県メディカルセンターの岩田誠司氏も交え、会場全体で今回の反省点を次回にどう生かすか、活発なディスカッションが行われました。
またそれに先立ち、6月28日には院内の移植医療実施報告会を開催しました。報告会は、職員が移植医療への理解を深め、移植医療を実施する上での問題点や今後の展望を検討するために開かれたもので、100人を超える職員が参加しました。移植医療に携わる医師、看護師、コーディネーター、薬剤師など13人の職員が、これまで実施してきた22例の生体腎移植と3例の脳死下臓器提供について、その時に感じたことや苦労したこと、これからの展望など、それぞれの思いを語りました。
当院の移植医療に対する活動について、生体腎移植に取り組む移植外科の谷口雅彦診療部長は「僅か1年半で22例の生体腎移植を行うことができたのは、各職種の方々のご協力の賜物だ」と話しました。また、脳死下臓器提供管理委員会の福田賢治委員長(脳神経センター長)は脳死下での臓器提供について「尊厳を守りつつより良き医療を目指すことが重要だ。脳死下臓器提供を推進する土台には終末期医療がある。今後は終末期医療のあり方も議論しながら進めたい」と話しました。
活発に議論する聖マリア病院の職員たち(7月13日の検証会) -
2017.06.12 第9回聖マリア病院緩和ケア研修会を開催
聖マリア病院は6月10、11の両日、がん診療に関わる医師に対する緩和ケア研修会を開催しました。この研修会は、国指定の「地域がん診療連携拠点病院」として、がん診療に携わる主に筑後地区の医師を対象に緩和ケアの基本的な知識、技術を修得してもらうために2009年以降、毎年開いています。
9回目となる今回は、院内外の医師37人が基本知識を学ぶ講義を受け、事例をもとにしたワークショップや3人1チームに分かれて患者に病状説明を行うロールプレイなどに取り組みました。
参加した医師らは「患者さんと接する際に配慮すべき点など新たな視点が得られた」などと研修会の意義を評価。修了式では、当院緩和ケアセンターの今村豊センター長が「受講者には2日間のタイトな研修日程の中、熱心に取り組んでもらった。今後、がん患者さんの対応に際しては研修の成果を生かしてほしい」と総評を述べました。
聖マリア病院で開かれた緩和ケア研修会 -
2017.06.08 感染症対策実地訓練を実施
聖マリア病院は6月7日、久留米市内で新型インフルエンザ疑い患者が発生したことを想定した感染症対策実地訓練を行いました。この訓練は第二種感染症指定医療機関として、2類感染症および新型インフルエンザなどの発生時に、迅速かつ適切に対応するために、久留米市保健所の協力で毎年実施しています。
訓練には当院のほか、市保健所、筑後地区の病院から約30人が参加。市内在住の男性が海外で新型インフルエンザ疑いの患者と接触。帰国後、男性本人に発熱や呼吸器症状が現れ、新型インフルエンザの疑いがあるとして、市保健所から当院地域医療支援棟13階の感染症病室までの搬送や入院後の診察、検体採取などの流れを確認しました。
訓練後は、参加者による意見交換会を実施。当院医療の質管理本部の馬場千草師長は「慣れない防護具をつけ、普段と違う手順で行う問診や診察は戸惑うことも多い。今回の反省点を踏まえ、いつか本当の感染症患者を受け入れる状況になったときに慌てず焦らず対応できるよう、今後も訓練を積み重ねていきたい」と総括しました。
検体採取の様子
訓練後の意見交換会では改善点などを活発に議論しました -
2017.04.21 第85回 聖マリア病院地域医療支援講演会を開催
聖マリア病院は4月21日、第85回地域医療支援講演会を開催しました。「あすの診療に役立つ教育講演」をコンセプトに当院職員と連携登録医向けに開催しているもので、今回は一般演題「聖マリアヘルスケアセンター生活習慣病科における骨粗鬆症治療に対する取り組み」(演者:聖マリアヘルスケアセンター、福井卓子生活習慣病科診療部長)、特別講演「糖尿病の骨粗鬆症 どうやって治療するか」(演者:医療法人新生会高田中央病院、斉藤美恵子糖尿病内科部長)の二部構成。
福井医師は、近年増加している大腿骨近位部骨折により健康寿命が短くなることを指摘し、骨粗鬆症の早期発見や治療介入への日ごろの取り組みについて話しました。斉藤医師は、骨粗鬆症の発症が糖尿病と深く関連しており、骨粗鬆症が老化だけでもたらされるのではなく、適切な治療をすることで骨粗鬆症による骨折や寝たきり状態を減らすことが可能であると訴えました。 -
2016.12.06 布井糖尿病センター長に鈴木万平賞
第10回鈴木万平賞(2017年度)が聖マリア病院糖尿病センター長の布井清秀医師に贈られることが決まりました。公益財団法人鈴木万平糖尿病財団が贈るこの賞は、糖尿病療養指導に積極的に取り組み、治療や予防に著しく貢献した個人、団体を顕彰するもので、この分野では国内で最も権威ある賞の一つとされています。
布井氏は、1987年から日本糖尿病協会福岡県支部の再編に取り組み、100カ所以上の「友の会」を設置するなどさまざまな改革を行い、現在の県糖尿病協会の基盤を構築。97年以降は、筑後地区や佐賀県に糖尿病療養指導士認定委員会を設立し、地域での療養指導士制度の基礎を築きました。この間に制作した研修カリキュラムなどは全国に広がり、資格取得後の研鑽の場として地域糖尿病療養指導士会を立ち上げました。布井氏らを核にした福岡県糖尿病療養指導士会の活動は第1回鈴木万平賞・団体(2007年度)に結実しました。
今回の受賞決定について布井氏は「医師とメディカルスタッフ、患者を含む全員が同じ地平に立ち、カを合わせれば強くなれることを実践してきた証になります」と語り、専門医が少ない問題の解決策の一つとして進めてきた療養指導士制度の維持と地域医療へのさらなる貢献に意欲を燃やしています。
布井氏は1949年生まれの67歳。九州大学医学部卒業。91年に当院の糖尿病内分泌内科診療部長として入職、95年副院長に就任し、2015年から現職。

布井清秀・糖尿病センター長 -
2016.12.03 国際医療協力を考える学術大会
「民間から発信する国際保健医療」をメーンテーマに、日本国際保健医療学会学術大会(大会長=浦部大策聖マリア病院国際事業部長)が2016年12月3、4両日、久留米シティプラザ(福岡県久留米市)で開催され、海外13カ国を含む約600人が参加しました。熊本地震をテーマにした初日のシンポジウムでは、被災地でさまざまな医療活動に取り組んだシンポジストが、避難所内のプライバシー保護や感染症対策などの重要性を指摘、普段からの周到な備えを怠らないよう訴えました。2日目の市民公開講座では、九州大学大学院医学研究院の二宮利治教授が「健康長寿を目指す上での日本の課題~久山町研究の成績より」と題して講演。学術大会に隣接した会場では、発展途上国での母子栄養改善活動をテーマにしたセミナーも開かれました。 -
2016.12.03 チャリティーコンサート開催
熊本地震被災地の完全復興を願うチャリティークリスマスコンサートが2016年12月3日、聖マリア病院敷地内の「雪の聖母聖堂」で開かれました。主賓の久留米音協合唱団、正副両指揮者によるア・カペラ(無伴奏)での6曲を演奏。客演指揮者の安積道也氏(西南学院音楽主事、オラトリオ・アカデミー常任指揮者)はオルガン独奏に続いて、オランダの作曲家、J.P.スウェーリンクの名曲「今日キリストはお生まれになった(Hodie Christus natus est)」など合唱曲4曲を披露、最後は入場者全員で聖歌「しずけき」を合唱しました。献金37,390円は、宗教法人カトリック中央協議会カリタスジャパンを通じて熊本地震復興支援に役立てられます。皆様のご協力に感謝いたします。 -
2016.11.07 ISAPHがODA白書に登場
聖マリア病院の経営母体である社会医療法人雪の聖母会は長年、保健・医療分野での国際協力に取り組んできました。グループ傘下のNPO法人ISAPH(International Support and Partnership for Health=アイサップ)が国際協力機構(JICA)の草の根技術協力プロジェクトとして推進してきたアフリカ・マラウイ共和国での乳幼児栄養改善事業(2013年5月~16年5月)もその一つです。この取り組みが最新の「国際協力白書(ODA白書)」(16年5月発行)に紹介されました。
マラウイはアフリカ大陸南東部に位置する内陸国。経済基盤が脆弱で、1人当たりの国民総所得はわずか270米ドル(2013年世界銀行調べ)、1000人出産当たりの乳児死亡率は44人(世界保健統計2015)という世界で最も貧しい国の一つです。
今回の国際協力事業の目的は、このマラウイ北部ムジンバ県を中心とする地域の乳幼児の栄養状態が悪いのはなぜか、その改善にはどのような対策が有効なのかーといったことを把握すること。現地派遣のプロジェクトメンバーらは、離乳食レシピの普及や乳幼児の成長計測方法の改善、栄養不良児の治療など、さまざまな活動を行い、データを集めました。調査する乳幼児を100人に絞ったことなどから年齢別データにばらつきがみられ、厳密に評価できませんが、試行としての成果を得ることができました。主な成果としては、マラウイの保健制度の課題とその解決法を行政当局に提案した、乳幼児成長計測のボランティアを育成し、迅速・正確に発育状態が把握できるようになった、成長計測の参加率が80%に倍増、効率的な健康教育ができるようになった、栄養についての知識が普及し、完全母乳育児の割合が55%から93%に向上した、離乳期の食事内容がより豊かになった-などの点が挙げられます。
国際協力白書では、こうしたマラウイでのISAPHの取り組みについて「地域の母親グループを立ち上げて、バランスのとれた離乳食の作り方を教えるとともにその普及を図り、また、子供の病気の予防、病気にかかったときの通院治療の必要性といった知識普及を根付かせてきています」と評価しています。記事には、聖マリア病院がマラウイ政府からの要請に応えて寄贈する保育器4台の写真も添えられています。

2016年度国際協力白書に囲み記事で紹介されている
ISAPHの「子どもにやさしい地域保健プロジェクト」